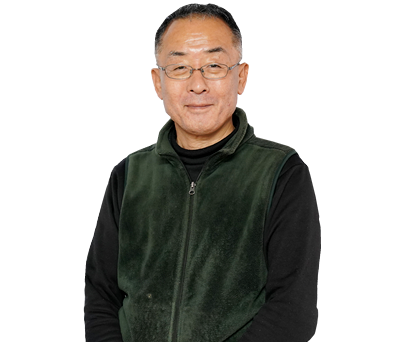
こだわり料理で「ほっと」できるお店店主こだわりのどら焼きやおでん、スモークチキンなどを季節感と共に楽しんでいただけます。また小さなお子様からご年配の方、男女問わず楽しい時間を過ごせる店作りを目指しています。お酒の飲めない方でも楽しめる料理などもご用意していますので、ぜひご来店ください。

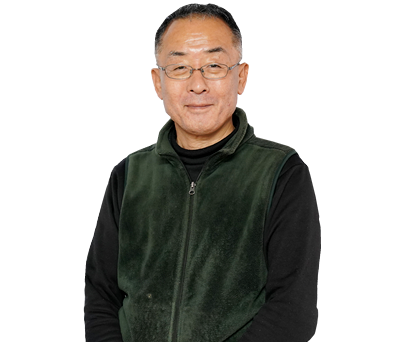
こだわり料理で「ほっと」できるお店店主こだわりのどら焼きやおでん、スモークチキンなどを季節感と共に楽しんでいただけます。また小さなお子様からご年配の方、男女問わず楽しい時間を過ごせる店作りを目指しています。お酒の飲めない方でも楽しめる料理などもご用意していますので、ぜひご来店ください。